ブログ
2025.12.24
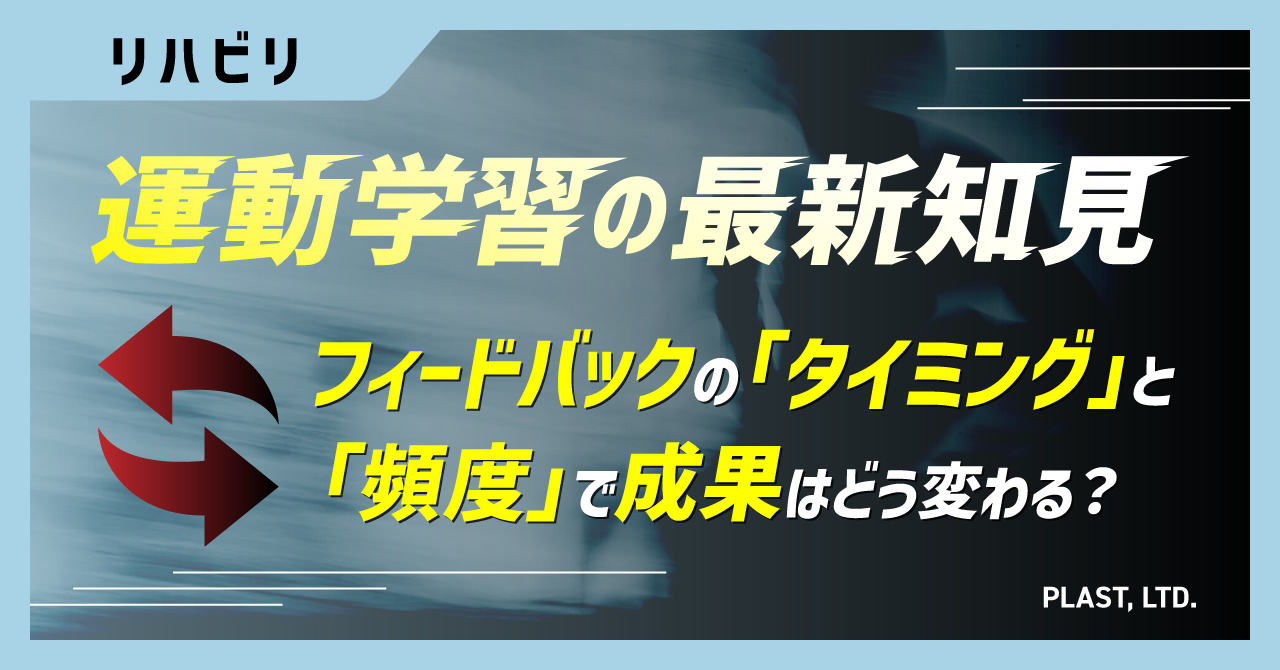
人は動きを学ぶとき、筋力や柔軟性だけではなく“情報”を使っています。
情報とは、セラピストの声かけ、鏡で見る映像、身体の感覚、成功・失敗の結果など、すべてが含まれます。
この“情報=フィードバック”の扱い方によって、動作改善のスピードも、学習の定着度も驚くほど変わります。筋トレのセット数よりも、実はフィードバック設計の方が成果を左右することが多い。これは近年の運動学習研究で強調されている視点です。
ここでは、最新の知見から「タイミング」と「頻度」の2つに絞って整理します。
フィードバックには大きく2種類あります。
① KR(Knowledge of Result:結果の知識)
・“歩行速度が○%上がりました”
・“的から3cmずれました”
結果の情報を伝えるもの。
② KP(Knowledge of Performance:動作の知識)
・“膝が内側に入っています”
・“体幹が先に動いています”
動作そのものについて指摘するもの。
若手セラピストが陥りやすいのは、KPを与えすぎてしまうことです。
“教えすぎると学習が阻害される”という研究は山ほどあります(Winstein & Schmidt, 1990)。
結論から言うと、
・初期:リアルタイム(同時)フィードバック
・後期:遅延フィードバック
この組み合わせが最も学習効果を高めます。
動作の理解が浅い段階では、リアルタイムに方向づけを行った方が誤学習を防ぎます。
例えば、歩行中に膝が内側に入る人に、
「はい、今のタイミングで外側に押し返して」
など、動作中のガイドが理解を助ける。
MRI研究では、初心者は視覚情報を脳の“後頭頂葉ネットワーク”で処理し、それが運動制御系に直接つながることが示されています(Seidler et al., 2010)。
リアルタイムで情報を流すことで、この連結が強化されるという考え方。
ある程度できるようになったら、動作後にまとめてフィードバックする方が“自分で気づく力”が育ちます。
Schmidt & Lee(Motor Control and Learning, 2019)は、
遅延フィードバックは自己評価を促し、長期記憶の定着に優れる
と述べています。
臨床でイメージすると、
学習後に
「今の動き、どこが良かったと思いますか?」
と問い、患者自身がプロセスを言語化できるかがポイント。
運動学習の世界では有名な結論があります。
Winstein & Schmidt(1990)の研究は象徴的で、
・100%の頻度でフィードバックを与えた群
・50%の頻度しか与えなかった群
を比較すると、学習の保持テストでは後者(50%)の方が成績が良かったという結果。
理由は単純で、
与えすぎると自分の感覚を使わなくなるから。
筋トレを補助しすぎると筋力がつかないのと同じ。
フィードバックも“自力での誤差修正”を奪ってしまうのです。
最新研究で推奨されているのは、以下のモデルです。
動作理解を助ける段階
(例)毎回の試行で短くKPを入れる
(例)2〜3回に1回フィードバック
(例)患者本人が求めたときだけ与える
→ “自立した学習者”としてのスキルが育つ
**自己選択型フィードバック(Self-controlled feedback)**は、Wulfらの研究で
動機づけ・自律性を高め、パフォーマンスが向上する
という知見があります(Wulf & Lewthwaite, 2016)。
臨床ではKP(動作の説明)が増えすぎる傾向があります。
しかし、研究から言える黄金比はこうです。
“膝が入っています”ではなく
“膝を外へ押す方向性”
のように、1つのポイントに絞る。
“成功・失敗の結果”に注目させる。
結果から自分の動作を推察できるようにする。
これが長期保持につながる。
いきなりKPを細かく言いすぎると、動作がぎこちなくなる
(constrained action hypothesis, Wulf, 2001)
というのは、若手ほど陥りやすい落とし穴。
ここまでの知見を、すぐに使える言葉に翻訳します。
「いま、ここを意識して」
「はい、そのタイミングで伸ばして」
「今の動き、どこが良かった感じがします?」
「変化に気づいたところはありますか?」
「必要なときだけ声かけしますね」
「結果を見て、自分なりに修正してみましょう」
声かけは“指示”ではなく“気づきのガイド”であるほど効果が高まります。
フィードバックのタイミングと頻度は、動作改善における“見えないデザイン”です。
・教えすぎると自立を奪う
・早期はリアルタイム、後期は遅延
・頻度は徐々に下げる
・KP → KRへと移行する
・自己選択型フィードバックは最強の武器
筋力や可動域以上に、“情報の渡し方”そのものが運動学習を左右します。